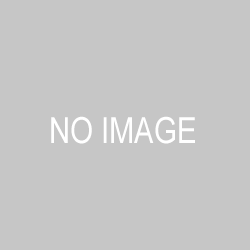名古屋市天白区のhumさまにて、出張ビワの葉エキス作りワークショップを開催いたします。
【日 時】2025年10月19日(日)13:00〜15:00
【参加費】5,400円(材料費・税込み)
【定 員】5名
【場 所】hum
名古屋市天白区平針2丁目211 山田平針ビル101
【内 容】
ビワの葉エキス作り ※作ったエキスはお持ち帰り
びわ茶・お茶菓子・すぐに役立つプレゼント付き
【お申し込み】
公式LINE、公式インスタグラムDMでのご連絡か、
090-1750-0468(林)へお電話ください